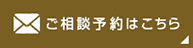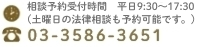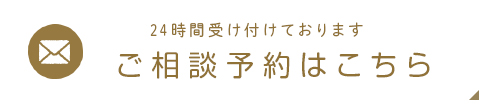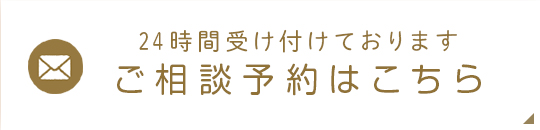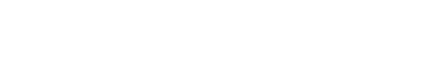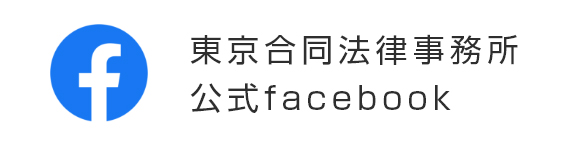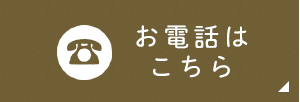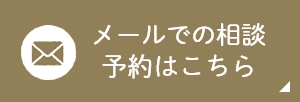弁護士 坂勇一郎
10月1日の消費税増税への動きを背景に、キャッシュレス決済の宣伝や報道が増えています。身の回りでも、キャッシュレス決済をつかう人々が増えていますが、他方、キャッシュレス決済には不安があるので利用を控えている、金額を抑えている、銀行預金につながらないようにしている、等の声もよく聞きます。
<キャッシュレス決済への「不安」>
こうした声には理由があります。例えば、キャッシュレス決済が無権限の第三者により不正利用された場合、利用者は、必ずしも救済されるとは限りません。利用規約での不正利用の場合の責任分担の定めはまちまちで、利用者保護に厚い規定とする業者もありますが、中には、不正利用の場合に利用者に責任を負わせることを原則としている業者もあります(注1) 。
慎重な利用者は、利用規約を確認したうえで、決済事業者を選ぶこともできますが、多くの利用者にそのような選択を求めるのは、あまり現実的でないように思います。
<キャッシュレスの現状>
最近目立つのは、スマートフォンへのフィッシング詐欺事例です(注2) 。また、海外旅行でカードを盗まれた、海外で昏睡強盗にあってスマートフォンを盗まれた等、海外の紛争事例も目立ちます。紛争事例の中には、本人に落ち度がないとは言い切れないものもありますが、被害にあった利用者が全額負担を強いられるというのは、特に被害額が多額の場合、酷なように思われます。
犯罪グループ等の攻撃側は、相当に技術力を高度化させ、ノウハウを蓄積しています。IDやパスワードを盗取とみられる事例も後を絶ちません。このような状況に対して個々人で防御するには限界があります。
少し前には、大手コンビニチェーンのキャッシュレス決済の不正利用とサービス提供停止が社会の耳目を集めました。キャッシュレス決済業者は、顧客獲得のために目先のサービスや利便性の売込みには熱心ですが、安全・安心よりも利便性を優先しがち、ともすると安全・安心は後回しになりがちであることも、懸念されます。
<不正利用と民法の原則>
民法の原則では、本人が決済を行っていない以上、本人は責任を負わないはずです。もっとも、決済事業者のシステムがしっかりしていて、本人に過失があるなどの場合には、本人が責任を負うことになる場合があり得ます(注3) 。
利用規約のうち、本人に過失がない場合も本人負担としているものは、消費者契約法上無効になり得ます。ですが、決済事業者が簡単に無効と認めてくれるかは、わかりません。
本人に過失がある場合には、民法によっても、本人が責任を負うことはやむを得ません。このような考え方に基づいた利用規約を無効とするのは難しいと思われます。ですが、軽度の過失のときには、少なくない事例において本人に全額の負担を負わせることは酷なように思われます。
<預金の不正出金と預金者保護法>
もはや20年前のことになりますが、当時、キャッシュカードの偽造・変造、盗取などにより、預金の不正出金が相次ぎ、被害者が多額の損害を負わされることが社会問題となりました。そこで、2005年に預金者保護法が制定され、不正出金の場合の責任は原則として金融機関が負い、利用者は軽過失の場合も4分の1の範囲のみの負担とされました。預金者保護法により、利用者には安心して預金取引を行う環境がもたらされるとともに、金融機関に不正出金対策の取組みをさらに促す重要な契機となりました。
<安全・安心とキャッシュレス決済>
この間、利用者が安全・安心を求める声は高まっているように思われます。特にわが国では、安全・安心に疑問があり得る商品やサービスは、その拡大に大きな限界があります。
キャッシュレス決済の普及を図るのであれば、安心・安全に対する「不安」を乗り越えることが必要なのではないでしょうか。安全・安心を犠牲にした利便性でなく、安全・安心が確保された利便性が求められているように思います。
<金融制度SG報告書と日弁連意見書>
金融庁は、本年7月、決済と金融仲介に関する審議会報告書を公表しました(注4)。報告書の中では、不正利用がされた場合の責任分担のルールについて検討することが適当と提言されています。
この報告書の公表を受けて、日本弁護士連合会は、本年9月、意見書を公表しました(注5)。意見書の中では、不正利用について、「利用者が責任を負わないことを原則としつつ、過失のある利用者の責任を一定額に限定するルールを横断的に設けるべき」ことが提言されています。
今後、決済に関する法制度の整備に向けた議論がさらに具体化され、来年の通常国会には、改正法案が提出されるとみられています。
決済法制を巡ってはさまざまな意見があり得ますが、利用者の安全・安心が確保された決済法制を実現すべく、引き続き尽力していく所存です。みなさんも、ぜひ、決済のあり方について関心を持ち、安全・安心の決済制度、決済サービスが実現・拡大していくように、利用者としての行動をとっていただきたいと思います。
<万が一のときには>
不幸にして万が一、決済カードやスマートフォンを紛失したり、盗難にあった場合には、直ちに決済業者に連絡をして利用停止を求めるとともに、警察への届出等必要な対応をとることが大切です。また、できるだけ早く消費生活センターに相談をしてみることをお勧めします。
(追記)
キャッシュレス決済については、加盟店がキャッシュレス業者から不適切な扱いを受けることを防ぐ課題、個人情報保護や情報の適切な利用に関する課題も重要です。これらについては、他日を期したいと考えます。
---------------
(注1):キャッシュレス推進協議会は「コード決済における不正利用に関する 責任分担・補償等についての規定事例集」(2019年8月)を公表している。
(注2):https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190826/k10012049231000.html
(注3):表見代理や準占有者への弁済。
(注4):https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190726.html
(注5):https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2019/190912.html 同意見書では、無権限者による不正利用のルールの他、加盟店管理制度や、加盟店に問題がある場合の返金ルール等についても、提言している。