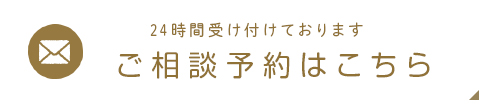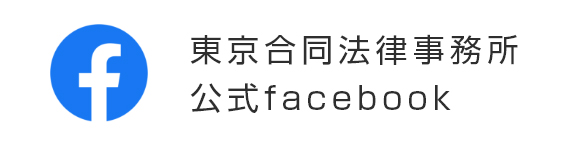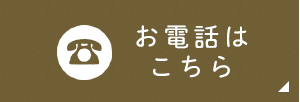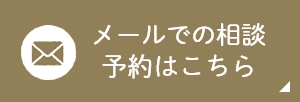日本版「司法取引」の施行開始から1年
昨年(2018年)6月1日,可視化制度の導入や盗聴法の拡大などとともに,2016年改正刑訴法の“目玉”として新設された日本版「司法取引」が,いよいよ施行された。
新たに導入されたこの日本版「司法取引」制度は,他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るという「捜査公判協力型」の司法取引であり,「密告型」の司法取引というべきものである。他人を密告したことで利益を得られるということは,そのような利益にあずかるために無関係の他人を巻き込んでしまう危険性がある。日本でも,これまで捜査機関によって事実上行われてきた「闇取引」によって,数多くの冤罪が発生してきた(「日本版『司法取引』を問う」2015年旬報社刊参照)。
日本版「司法取引」の施行開始から1年が経過した今,現実にどのような事件に「司法取引」が利用されているのだろうか。そして,導入にあたって懸念されてきた新たな冤罪の危険性は,完全に払拭されたのだろうか。
適用事例第1号-MHPS事件
2018年7月20日,東京地検特捜部は,三菱日立パワーシステムズ(MHPS)によるタイでの火力発電所建設に絡み,同社元幹部3人を不正競争防止法違反(外国公務員に対する贈賄)で在宅起訴するとともに,同社については,東京地検特捜部に対して捜査協力をした見返りとして不起訴とした。このMHPS事件が,日本版「司法取引」適用事例の第1号とされている。
しかし,そもそも「司法取引」を導入した目的は,法制審でもさんざん議論されたことだが,組織犯罪における黒幕処罰の必要性だったはずである。それゆえ,適用が想定される事例としてあげられていたのが,いわゆるオレオレ詐欺における末端の「受け子」「出し子」に恩典を与えて,実際に指令を下して多額の利益を貪っている黒幕を処罰するというものであった。ところが,MHPS事件は,要するに,現地の役人に賄賂を贈って事業継続をしようとした役員個人を法人自ら告発し,検察に捜査協力をすることで,法人そのものが恩典を得るというものである。法人処罰を逃れるため,その法人の事業遂行のため動いてきた個人の処罰に法人が協力するというのであるから,「トカゲの尻尾切りのために制度が利用された」との批判も,あながち嘘ではない。いずれにしても,当初の制度目的が黒幕処罰であったことからすれば,適用事例第1号がそれとはまったく違った目的のもとでの適用となったことは間違いない。
なお,MHPS事件で起訴された3人のうち,2人は起訴内容を認め有罪判決が言い渡されたが(東京地裁2019年3月1日判決),もう1人は無罪を主張し分離公判で争っており,今後,「司法取引」における合意内容の信用性が,初めて公判で争われるものと思われる。
適用事例第2号-カルロス・ゴーン氏の事件
そして,日本版「司法取引」適用事例第2号とされているのが,2018年11月以来,世間でも大きく注目されている日産元会長のカルロス・ゴーン氏の金融商品取引法違反・特別背任事件である。同氏の事件については,最初の起訴の後,なかなか保釈が通らず(その後弁護人の交代,保釈決定,保釈後の再逮捕),身柄拘束の長期化,人質司法の現状は国際的にも強く批判されているが,同氏の起訴内容を裏付ける証拠として,日産社員と検察との「司法取引」による合意があったことも注目されている。
もっとも,カルロス・ゴーン氏の事例については,未だ公判の目処はたっておらず,誰とどのような「司法取引」がなされたのかなどの事実関係が明確になっていないことから,現時点でその内容を評価することは難しい。しかし,同氏も弁護人も起訴内容については全面的に否認しており,今後開かれる公判での攻防については,その進展を注視してゆく必要がある。
日本版「司法取引」の今後と批判的視点の必要性
日本版「司法取引」が制度化されたとき,筆者は,「法務検察としては,制度の運用が現実化すれば,まずは財政経済事犯のなかでも,比較的件数の多い組織的詐欺や貸金業法違反などの一般事件から“成功例”を出して,根付かせて行くことを考えているのかもしれない」としていた。しかし,これまでに起訴された2つの適用事例を見る限り,検察(特に特捜部)が制度の定着を計ろうとしていることは間違いないものの,法制審などで典型例としてあがっていたオレオレ詐欺のような一般事件ではなく,大企業を舞台とした大規模事件に限定しているようにもみえる。
もっとも,このような適用傾向が今後も継続するのかは定かでない。現時点では,世論の多くが「司法取引」の問題性を意識せず,大規模事件における検察側立証の要として用いられたことについて,むしろ好意的ですらある(元検察官の郷原信郎氏は自らのブログで,MHPS事件に「司法取引」が適用されたことに“違和感”があると述べつつも,法人処罰を従来のように個人処罰の副次的なものと捉える従来の考え方から,個別に捉える考え方へと変化する契機になるのではないかと述べ,一定評価しているようである。)。
しかし,密告型「司法取引」による巻き込み型冤罪発生の危険性を完全に払拭する有効な手立ては存在しない。特に,司法取引によって「売られた」側の弁護人は,「売った」側の弁護人の同意というある種の“お墨付き”を得た供述を弾劾しなければならず,極めて困難なたたかいを強いられることになる。
さらに,新たな制度の有用性は,簡単に危険性へと転嫁することを忘れてはならない。大規模な経済的事件への適用「成功例」の賞賛は,今後適用される可能性のある別種の事件への無批判な適用を許しかねない。その別種の事件が,市民として身近に感じられない大企業の事件などではなく,民主的な組織にまで対象を拡げることも十分ありうる。
私たちは,今後も日本版「司法取引」が,新たな冤罪を生む危険性をはらんだ制度として存続していないか,常に批判的視点をもって,検証し続けてゆくことが必要であろう。
(2019年5月21日)