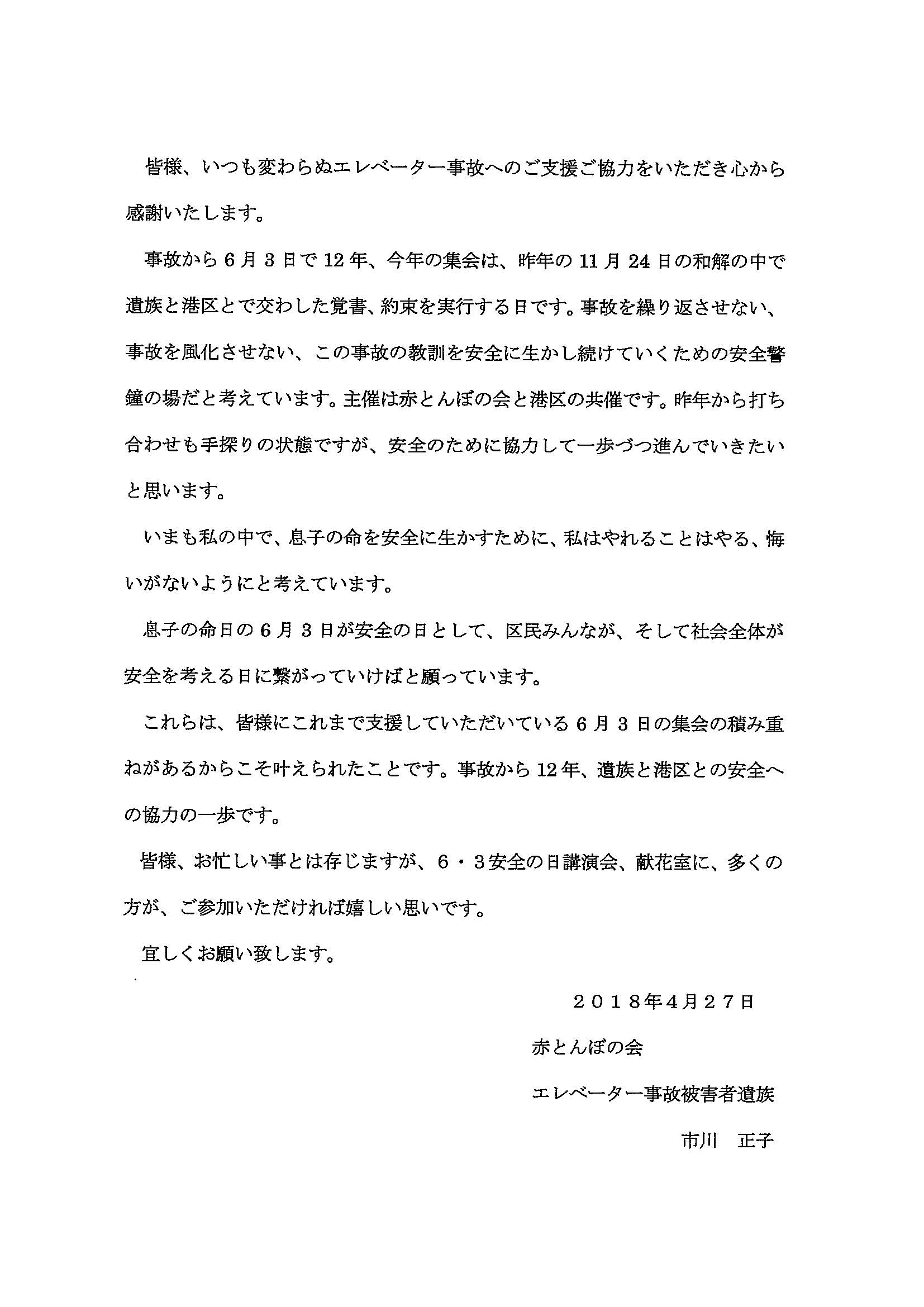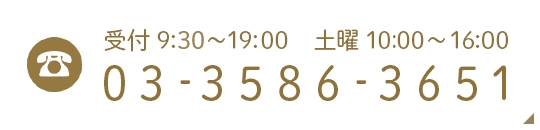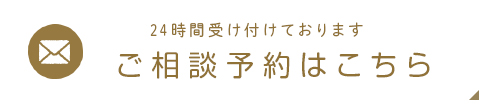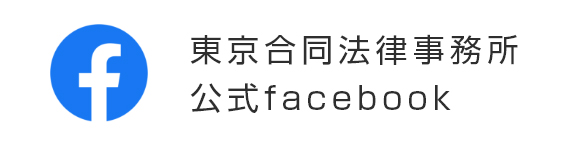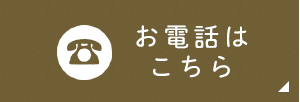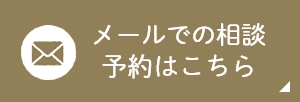弁護士 泉澤章
日本版「司法取引」の施行開始
今年(2018年)6月1日から日本版「司法取引」がいよいよ施行されます。施行を前にした今年3月16日には,政令で定めることになっていた財政経済犯罪(刑事訴訟法350条の2第2項2号)について閣議決定がなされました。政令では対象となる「特定犯罪」に,脱税や独禁法違反,金融商品取引法違反,特許法違反,貸金業法違反,破産法における詐欺破産,会社法の特別背任などがつけ加えられることになりました。また同月19日に最高検は,全国の地検と高検に基本的な運用方針をまとめた通達を出しました。
日本版「司法取引」制度の特徴
日本版「司法取引」制度は2016年,可視化制度の導入や盗聴法の拡大などとともに刑事司法制度改革によって新設されました。その特徴を一言でいえば,自ら犯した犯罪事実を取引材料にして自ら不起訴や刑の減免を得る,いわゆる自己負罪型の取引ではなく,他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るいわゆる捜査公判協力型の司法取引であるということです。捜査公判協力型などと小難しくいえば聞こえはいいですが,要は他人を「売る」ことであり,「密告型」の司法取引といってもいいでしょう。
自己負罪型司法取引の典型例として,アメリカの司法取引が良くあげられる。重い罪を犯した犯人でも罪を自ら認めれば軽い刑で済むという,テレビや映画にも良く出てくる制度です。重罪を犯していることが確実なのに軽い罪ですぐ釈放されてしまうというところに,腑に落ちない日本人は多いと思われますが,アメリカではこうでもしないと大量の刑事事件を処理することがおよそ不可能であると言われているようです。
改正刑事訴訟法の成立過程で,日本では自己負罪型の司法取引ではなく,捜査公判協力型の司法取引を導入することに決まりました。日本で捜査公判型の司法取引制度が導入されたのには,この新制度の導入が,取調べ可視化制度の導入とのバーターであったことが大きく影響していると思われます。取調べ可視化制度の導入により,今までのように捜査段階で自白供述が採取しにくくなる(捜査側の主張であり,それが真実かどうかはともかく)。それゆえ,テロや暴力団など組織犯罪の黒幕処罰を進めるためには,これまでの取調べに頼った証拠採取方法ではない,新たな捜査方法が不可欠となり,そのひとつがこの捜査公判協力型司法取引であるというのです。
日本版「司法取引」が冤罪を生む危険性
確かに,他人を密告することで不起訴や刑の減免などの利益が与えられるなら,これまでよりも組織犯罪における黒幕処罰のための供述証拠は得られやすくなるかもしれません。改正刑訴法案の提案当時,法務検察がさかんに宣伝した点もそこにあるのでしょう。
しかし,他人を密告したことで利益を得られるということは,そのような利益にあずかるために無関係の他人を巻き込んでしまう可能性もありうるということになります。ここに他人の犯罪事実を密告する捜査公判協力型司法取引のもつ一番のデメリットがあります。そしてこのような危惧の現実性は,これまで法制度がないにも関わらず,あまた行われてきたいわゆる「闇取引」の実例からも証明済みです。
最近では,美濃加茂市長による収賄事件がこの「闇取引」による冤罪発生の事例のひとつにあげられます。この事件では,贈賄したとされる人物が他の詐欺案件について不起訴の見返りを得るため,市長への贈賄という虚偽供述を行ったのではないかと言われています。1審名古屋地方裁判所では贈賄したとされる人物の供述が信用できないとされて元市長は無罪となりましたが,高裁では逆転敗訴で有罪となり,最高裁で有罪が確定しました。贈賄側の人間が「確かに金員をわたした」と供述し続けている限り,その供述者が(闇取引とはいえ)不起訴などの利益を受けている場合であっても,供述の信用性が減殺される望みは薄いことをこの事件はあらわしています。
「司法取引」制度を推進する側は,虚偽の供述には懲役刑(5年以下)の罰則を設けているから簡単に虚偽の取引はなされないし,「司法取引」をする協議・合意には弁護人の立会いが不可欠とされていることから,虚偽の取引が無辜の人を巻き込む危険性は低いといいます。しかし,虚偽の取引に罰則があるということは,いったん虚偽の取引をしてしまった者が引きかえすことを,かえって困難にしてしまいかねません。弁護人の立会いが不可欠だといっても,それはあくまで取引をする側であって,取引の対象となる者が,取引されることを事前に知って弁護人に相談することなど到底不可能であり意味がないのです。
日本版「司法取引」に対してどう向き合うべきか
このような危険性のある「司法取引」制度に,私たち法律家はどう向き合うべきなのでしょう。これは,「司法取引」をする,またはされた一般市民の方々にとっても,弁護士にどうアドバイスを受けたらいいのかを考えるうえで,重要なことといえるはずです。
「司法取引」制度は,取調べ可視化制度の導入と引き替えに,新たな捜査手法として法務検察の肝いりで取り入れた制度です。法務検察としては,制度の運用が現実化すれば,まずは財政経済事犯のなかでも,比較的件数の多い組織的詐欺や貸金業法違反などの一般事件から“成功例”を出して,根付かせて行くことを考えているのかもしれません。テロ組織や暴力団組織の関連事件への運用では,多くの国民が賛意を示すこともあるでしょう。しかし,この制度の運用が成功すればするほど,将来的には民主団体への弾圧手段として“応用”される危険性が高まることも間違いありません。
制度が運用され始めれば,自ら利益を受けるために取引に応じたいとする被疑者の弁護人となることも避けられない場面が出てくるでしょう。その反面,取引の対象となった被疑者・被告人の弁護人となることもあるでしょう。制度の危険性を知るならば,いずれの弁護人になったとしても,冤罪を生む可能性があることを常に念頭に置き,供述に偏重した捜査手法を批判することと同様,客観証拠を中心として,それとの対比で供述の信用性を検討する基本的な態度が,これまで以上に求められます。
盗聴法の拡大,共謀罪の成立と,これまで止めてきた刑事弾圧立法が次々と成立している今日こそ,刑事司法に関わる弁護士の真価が問われる時代になってきたのかもしれません。
この記事は泉澤章弁護士が執筆しました。【関連:刑事事件、施行から1年司法取引はどのように運用されているのか】