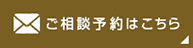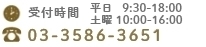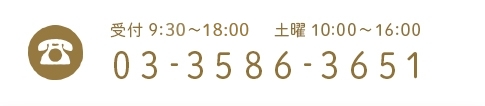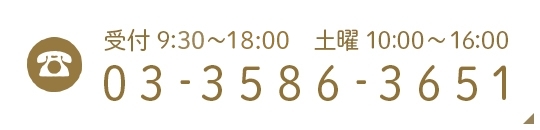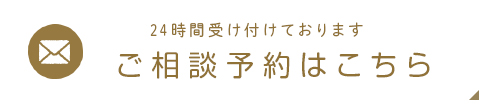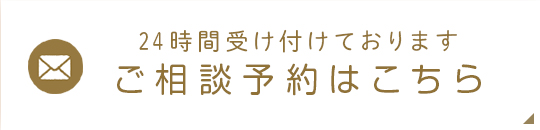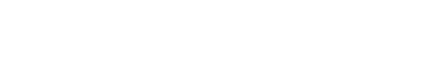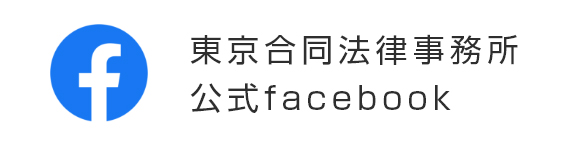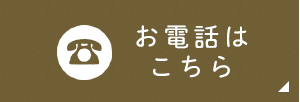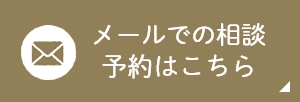ここでご紹介する文章は、私(泉澤章)が加入している法律家団体、自由法曹団の東京支部総会へ向けて報告したものです。再審制度は無実の人を救済する最終手段ですが、これまで多くの問題点が指摘されながら、戦後一度も改正されたことがありません。現行の再審制度がほんとうに無実の人を救済する法制度として機能するよう、私たちは法改正を強く求めています。ぜひご一読ください。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
再審法改正へ向けた取り組み
東京合同法律事務所 泉澤章
“再審法”改正の必要性
今年で事件発生から58年目となる袴田事件は、昨年3月に再審開始決定が確定し、現在静岡地裁で再審公判の審理が続いている。今年夏ころには、戦後5件目となる死刑再審の無罪判決が言い渡されるはずであると聞いている。犯人とされてきた袴田巌さんは、2014年の静岡地裁村山決定によって釈放されているものの、まだ完全な自由を得ているわけではない。再審無罪判決が確定することによって、袴田さんは名実ともに自由の身になる。そしてそれが実現するときは、もう目の前に来ている。
しかし、この状況を手放しで喜んでばかりもいられない。袴田さんは、今年3月で88歳になる。残された人生の時間は率直にいってそう長くはない。一刻も早い再審無罪判決が言い渡されるべきであるが、振り返ってみれば、村山決定が出てから今年で10年目にある。もし村山決定が確定して再審公判がすぐに始まっていれば、袴田さんは70代で完全な自由を得られたかもしれない。なぜもっと早く再審が開始され、もっと早く再審公判が始まらなかったのか。そこには、他の再審事件にも通じる、現行刑事再審制度(刑事訴訟法第4編の再審に関する規定、以下「再審法」)が抱える大きな問題が立ちふさがっている。
改正すべき2つの点
現行再審法が抱える問題のなかでも、特に重要な点の一つは、現行の再審請求審において証拠開示規定が存在しないことである。証拠開示規定がないため、現行法では担当裁判体が積極的に証拠開示を勧告しない限り、検察・警察側が保管している証拠を請求人が見ることはできない。しかし、再審請求審で積極的に証拠が開示された事件では、請求人に有利な証拠が発見され、それが再審開始に必要な新証拠となった例も多い。現行再審法のもとでは、結局、裁判体のいわば「当たりはずれ」で結論が決まりかねない。
もう一つは、一度高いハードルをクリアして再審開始決定が出ても、現行法では検察が異議申立てをすれば開始決定が確定せず、再審公判も開かれないことである。袴田事件も2014年の開始決定に対する検察官の即時抗告が認められていなければ、とっくに裁判は終わり、袴田さんの完全な自由はもっと早く訪れていたことだろう。異議申し立てを認めずとも、検察がどうしても争いたいのなら、再審公判で争えばよいのである。
このほかにも、現行再審法について改正すべき点は多々指摘されているが、少なくともこの2点については、早急に改正されなければならない。
再審法改正の機運の高まり
これまでも、現行再審法を新憲法の趣旨(人権救済規定)に則って改正すべきという運動は、日弁連を中心に続けられてきた。特に、白鳥・財田川決定以降、死刑再審4事件が次々と再審無罪となった1970年代から80年代にかけては、日弁連だけでなく、政党や労組、市民団体の強い支持によって、法案が国会で審議されたこともあった。しかしこの時は、法務・検察当局の強い抵抗と、白鳥・財田川決定の意味を矮小化しようとする裁判官らの動きに抗し得なかった。その結果、1990年から2000年代初頭にかけて“再審冬の時代”が訪れ、著名事件での再審開始決定がほぼ皆無となり、再審法改正運動も徐々に立ち消えてしまった。
風向きが変わったのは、2010年代に入ってからである。2010年の足利事件を皮切りに、布川事件、東電女性社員殺害事件、東住吉放火殺人事件、松橋事件、湖東記念病院事件と、立て続けに再審開始・無罪となる事件がマスコミを賑わせるようになった。死刑事件も、名張事件では後に取り消されたものの一度再審開始決定が出た。袴田事件では前述したように再審開始決定が確定している。このように、再審のいわば“新時代”をむかえたことで、再審に対する市民の注目も集まってきた。そこで、これら再審事件を支援してきた日弁連の人権擁護委員会を中心に、再審法のなかでも、現実の再審事件で特に問題となっている上記2点について、あらためて再審法を改正すべきとの運動を開始した。
再審法改正運動の現在地
日弁連では、2019年の徳島人権大会で、上記2点を含む再審法の改正を速やかに行いよう求める内容の決議を採択し、2022年には再審法改正実現本部(日弁連会長が本部長)を設置し、全国的な弁護士会の取り組みとして運動を進めている。また、日弁連だけではなく、市民団体では日本国民救援会が全国各地で再審法改正の意見書採択運動を強力に押し進めており、2023年末の時点で、実に170近い自治体で意見書が採択されている。
今年は袴田事件の再審無罪判決が確定するであろう年であり、再審法改正の気運が最も盛り上がるであろう年でもある。この機運を逃せば、再審法改正の実現はまた延びてしまいかねない。
東京三会でも、今年は再審法改正のシンポが予定されていると聞いている。日弁連で再審法改正運動を担っている団員は多く、また全国で再審事件の弁護にあたっている団員も数多い。ぜひ東京支部の団員も、積極的にこの運動へ参加していただきたい。
追記:この原稿を脱稿した直後、袴田事件弁護団長の西嶋勝彦先生の訃報が飛び込んできた。袴田さんの完全無罪判決を聞かずに亡くなられたことは、ほんとうに残念としか言いようがない。それとともに、もし2014年の再審開始決定に対して検察官異議申立てが認められていなかったら、とうに無罪判決を聞いていただろうにと、歯噛みする思いである。西嶋先生が最後まで強く求めていたこの再審法改正は、何としても私たちの手で実現しなければならない。
以上