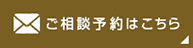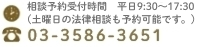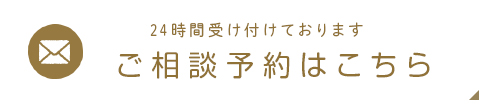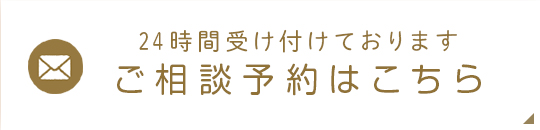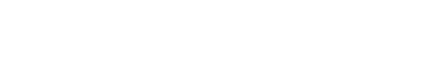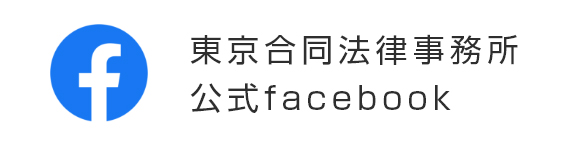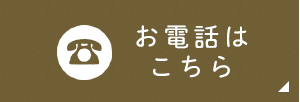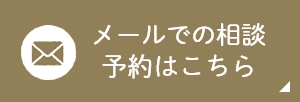① 改正相続法の施行日は2019年7月13日まで
本年(2018)年7月、民法(相続法)が改正されました。昨年(2017年)5月に民法(債権法)が改正されたのに続き、2年続けて民法が大きく変わることになりました。
施行時期を見ると、改正債権法の施行が2020年4月1日であるのに対し、改正相続法の施行は2019年7月13日までの日とされており、相続法の施行まで1年を切っています。
相続法の改正について、報道では配偶者居住権の創設が取り上げられることが多いですが、個人的に実務への影響が大きいのは遺留分の改正ではないかと思います。今回の改正で遺留分制度が大きく変わることになりました。
② これまでの遺留分制度
これまでは、相続人が、遺留分を遺言などで遺産を取得した人から取り戻そうとするとき、不動産など遺産の一部を物として取り戻すものとされていました(物権的効果)。遺留分の請求を受ける側で金銭で支払うことを申し出ることはできましたが(価格弁償)、遺留分を請求する側で金銭による支払いを求めることはできませんでした。
しかし、これでは権利が共有となって紛争が解決しないという問題があります。また、権利関係を複雑にしてしまうという問題もありました。
例えば、遺留分行使の結果、兄弟で不動産を、兄の持分1億1123万分の9268万1758、妹の持分1億1123万分の1854万8242で共有するといったケースがありました。私も実際にこのような判決を取って登記を移転したことがあります。
③ 改正後の遺留分制度
今回の改正では、遺留分の権利を金銭で請求できるものとしました(金銭債権化)。その結果、遺留分の行使として、〇〇万円を支払えという請求ができるようになります。シンプルになってよいと思いますが、今後これまでにはなかった次のような問題点も出て来ることになると思います。
遺留分を請求する側としては、〇〇万円を払えという判決を得たとしても、相手方に現金や預金がなければ、すぐに金銭を回収することはできません。相手方の不動産等を差押えて、競売にかけるなどの手続を別途取らなければなりません。
遺留分を請求される側としては、これまでは遺産である不動産の名義を移せばよかったところ、改正後は、そうはいかないことになります。金銭債権化により、遺産以外の自分の預金や自宅も差押えの対象となります。評価額が高いがすぐに売れないような不動産を遺言等で取得した場合、自己の財産から遺留分を支払わなければならないようなケースも出て来ると思います。
弁護士 瀬川宏貴