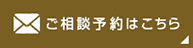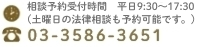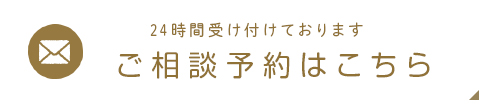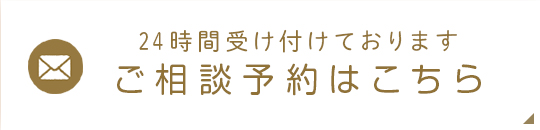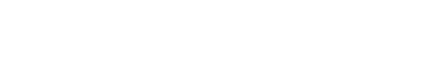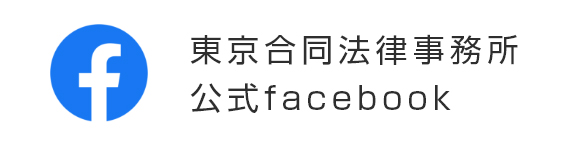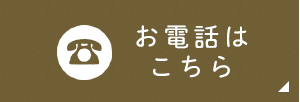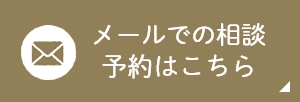1 毎年9月は防災月間であるとか。大正12年の関東大震災や、台風が到来しやすい時期であること等に由来して制定されたようです。今年もまた、台風情報に関するニュースが世上を騒がす時期となり、本コラムも、台風16号(「ミンドゥル」というそうです。)の日本接近が警戒されるという状況下で書いています。皆様、どうか十分注意を払ってお過ごしください。
2 こうした防災ということですが、現在では、各自治体がハザードマップを整備し、浸水被害警戒区域や土砂災害警戒区域などを区分して、地域住民に対し、非常時の警戒や避難等を呼びかけています。
他方で、防災体制が強化され、災害に対する備えが充実すればするほど、災害を受けたのは備えを怠った側が悪いのだという単純な自己責任論に結びつき、天災が人災に安易に転化してしまうことを危惧するコラムを一昨年書かせてもらいました。その想いは今も変わりはありません。
昨今の異常気象によって招来される激甚災害なるものに対して、それを防ぐために住民がその生活を根本から変更するなど事実上不可能だと思うからです。
3 さてそんな折、本年7月に発生した熱海の土石流災害について、遺族らが総額32億円を超える損害賠償の訴えを提起したとの報道に接しました。被告となったのは、土石流の起点となった場所の新旧土地所有者と、違法な盛り土造成を行ったとされる不動産管理会社のようです。
違法な盛り土が原因となって土石流災害が起きたのだとすれば、それは人災であり、その違法状態を惹起した者に対して責任追及を行うということは、自然の流れではあります。違法な盛り土ということは災害発生直後からマスコミ等で叫ばれていましたから、いずれこうした事態になるであろうことは、少しでも法律的素養のある者であれば、容易に予見しえたものであったろうと思います。
4 ただ、違法な盛り土→土石流の発生→近隣住民の被災・被害という因果の流れを立証することはそれほどたやすいことではありません。この点を立証するためには、地質学的知見や気象学的知見等々を駆使し、科学的観点から違法な盛り土によって土石流が発生し、住民が被害を受けたことを解明することが必要になると思われます。上記の原告団・弁護団の方々も、こうした因果関係の立証に向けて今後多大な労力と負担を注いでいくことになると予想されます。
そしてまた、こうした多大な労力と負担によって仮に事態の解明に至れたとしても、次は、32億を超えるような賠償責任を一個人や一企業が果たしうるのかという問題に直線せざるを得ないことになると推測されます。
5 こうしたことに鑑みると、人災だと強調することは、因果関係の立証が至極となって、あるいは、加害者とされる者の資力によって、被害者救済が立ち後れることになるのではないかという懸念が拭えません。
昨今の異常気象が地球温暖化という人類の活動の所産の故であることに思いを致すとき、それによって発生した激甚災害の結果もまた、人類が共同して引き受けるべきものではないかと思わずにはいられません。
その意味では、異常気象に基づく激甚災害が発生した場合には、まずは公的な事後救済がしっかりと図られなければならないのではないかと考えます。災害発生に何らかの寄与をした者がいる場合に、その者に対して何らかの求償を行うことがありうるとしても、その者に対する責任追及の可否や賠償額の如何によって、被災者が受けられる保護に差異や区別が設けられることになるのは、厳に避けるべきものでしょう。
今や異常気象による被災・犠牲は、いつ、どこで、誰が被ったとしても不思議ではありません。被災者ということの立場の互換性、そういったものに基礎を置く法制度の整備を望んでやみません。
以上
一昨年の記事はこちら:【コラム】予見可能性についての一考(台風被害に関連して)