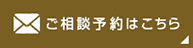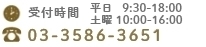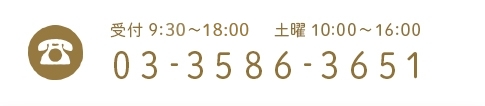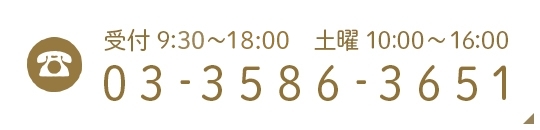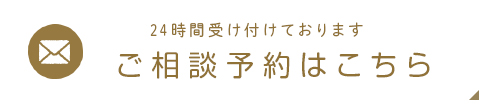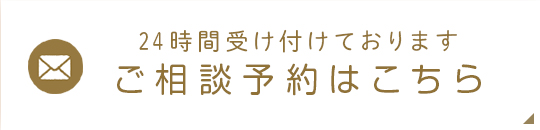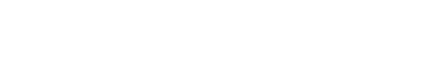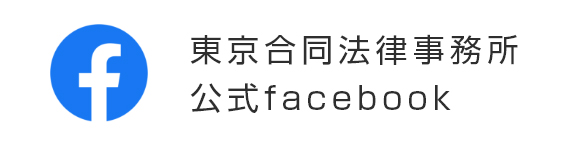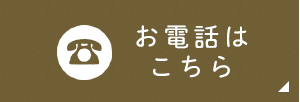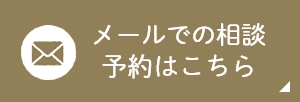わたしたちの事務所では、年に2度ほど「事務所学習会」を開いていて、哲学や歴史、科学など法律書以外をテキストに使っておこないます。先日の学習会では宮本常一『忘れられた日本人』(岩波文庫)がテキストでした。
そのなかに、「自分の持ち山が知らぬ間に官林になったり庄屋の山になったり、法律を知っていればどんなこともできる」であるとか「弁護士は三百代言といい法律をたてにとってウソばかり言ってみんなからお金をまきあげた」などというわたしたち弁護士にとって耳の痛い記述がでてきます。もちろん法律を知っていれば何でもできるわけではなく、多くの弁護士がウソをいってお金を巻き上げているものでもないのですが、人々の法律や弁護士に対するある種の感情を表現しているかと思います。法律や訴訟が巾をきかせていたり、弁護士の活躍する社会なんてとても幸せな世の中とは思われない、というのが弁護士であるわたしの個人的な思いではあります。
かつて「司法『改革』」が声高に叫ばれた時期がありました。「社会のすみずみまで法の支配を」とか「司法の容量をもっともっと」などの掛け声のもと、法科大学院の新設や弁護士の大量増員が実行されました。法曹・弁護士に対する需要はもっともっと増えるに違いない、そうでなくてはならないとばかり、わたしが弁護士になった頃と比べ弁護士数は倍増しました。
古典派経済学の用語に「セイの法則」というものがあります。供給は自ら需要を作りだすというもので、商品は作りさえすれば、価格調整機能がはたらき、売れ残りはいずれなくなる、供給はそれ自身の需要を創造するというものです。弁護士も大量に供給すれば、それに見あった法的な需要が生まれるといったおめでたい意見もありましたが、実際にはまったくそうはなりませんでした。
わたしたちの住む社会は、ファーストフード店のコーヒーで火傷したのは、熱すぎるコーヒーを販売した店の責任だとして損害賠償請求訴訟を起こすような社会ではなかったということでしょう。この国の人々は、「弁護士を大量に必要とする不健全な社会はいらない」というまっとうな結論を出しました。その結果、わたしたち弁護士は激しい競争にさらされることになりました。
2018.12.13更新
【コラム】幸せな社会と弁護士
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2024年12月 (1)
- 2024年06月 (1)
- 2024年04月 (1)
- 2024年02月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年07月 (1)
- 2023年06月 (1)
- 2023年05月 (1)
- 2023年02月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2021年06月 (2)
- 2021年04月 (1)
- 2021年01月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年09月 (1)
- 2020年07月 (2)
- 2020年04月 (2)
- 2020年03月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年07月 (1)
- 2019年06月 (2)
- 2019年05月 (2)
- 2019年04月 (1)
- 2019年02月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (2)
- 2018年09月 (2)
- 2018年08月 (3)
- 2018年07月 (1)
- 2018年06月 (2)
- 2018年05月 (3)
- 2018年04月 (1)
CATEGORY
- メディア (7)
- セミナー・イベントのご案内 (24)
- 書籍・論文・雑誌 (19)
- 法律コラム (55)
- とりくみ事件のご紹介 (17)
- 刑事事件 (24)
- 生業訴訟(「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟) (0)
- シンドラー社製エレベーター死亡事件 (4)
- 事務所のとりくみ (41)
- その他のコラム(エッセイなど) (9)
- 就任および入退所のお知らせ (5)
- 相続制度 改正特集 (16)